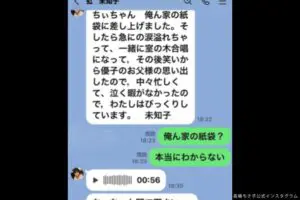大江健三郎さん逝去に世界のメディアも悲痛 「どんな絶望的な状況でも希望の灯を」
ノーベル文学賞作家の大江健三郎さんの訃報に、フランスのクオリティペーパー『ルモンド』にも追悼記事が掲載。大江さんの人柄に触れた。
■時代を直感する作家
電子版記事を英仏で読むと、各紙の名だたる記者が追悼文を書いており、フランスのクオリティペーパー『ルモンド』では御年82歳、1970年から52年にわたり日本で特派員をつとめる日本の特派員をつとめるフィリップ・ポンス日本支局長が記事を執筆。
ポンス支局長は 「大江健三郎という作家が、これほどまでに時代を直感したことはないだろう。大江健三郎は、その文学的キャリアと戦いによって、戦後日本の知的な歴史、その希望と失望の両方を体現していた」と追悼した。
■生前の印象を語る
生前に親交が深かった特派員が見た人柄としては「彼はまず第一に、誠実な人でした。友情に忠実で、自分自身にも忠実だった。1945年の敗戦後、日本が再建された価値観や思想(民主主義、平和主義)にも忠実だった。明晰で慎重な彼は、『真実』に関しては、憤慨し、じつに厳しい監視役であり続けた」と記す。
「時流に翻弄された大義を頑なに守る姿は、ときに感動的なドン・キホーテのようであり、忘却の毒を中和しようとするヒューマニズムに貫かれていた」
「『今日も昔も、知識人に突きつけられる唯一の真の問いは、人間の苦しみである』と、彼は何度か会ったときに話してくれたことがある。弱者、犠牲者、差別された人、忘れられた人への深い共感は、世紀末の柔らかいコンセンサスの日本に、異端とまではいかないまでも、不協和音を響かせるものだった」と弱者・犠牲者への深い共感があったとポンス支局長はつづる。
■欧米で高く評価される知識人
私が思い出すのは、2005年の秋だったか、セーヌ川左岸にあるパリ日本文化会館で大江健三郎さんが講演したときだ。
聴きに行くために一時間前に現場に行くも、並ぶのを毛嫌いするフランス人が行列をつくり、密になっているではないか。並ぶ人に伺うと、地方からわざわざ来た人も多く、500人も入れる会場は満席になり、私は拝聴できなかった。
2002年にはフランス政府から、ナポレオン1世が1802年5月19日に創設したレジオンドヌール勲章を受章した。繰り返し、欧州に飛び、世界の最高知性と歓談し、たいへん愛され、敬われた。
■どんな絶望にあろうと希望の灯を
2005年3月10日に大江さんが日本外国特派員協会で会見し、ご自身の最後の仕事が原発だとおっしゃった。辛酸を舐め続けるパレスチナの知の巨人サイードについて話し、大江さんは氏の本を編むほどに親しかった。
イスラエルの圧政にあり、苦しく哀しい状況を強いられながら、パレスチナで暮らすサイードについて「彼は絶望の淵にありながら、それでも常に楽観的だった」とおっしゃって、福島後に日本を絶望が覆うなかで、希望の灯を掲げようと諭され、特派員は感激して、拍手喝采し、賛辞をおくった。
生を授かった以上、いずれ死は訪れるが、何と哀しい別れであろうか。
大江健三郎さんの思想を受けて、私たちは希望を持ち続け、そして、希望を振り撒いていかなければならない。 長い抗いのため、さぞやお疲れでしょう。 どうか安らかにおやすみください。
Adieu Mosieur Kenzaburō Ōe.
・合わせて読みたい→サンド&氷川きよしがMC初タッグ『ニッポンの歌ヂカラ!』 豪華出演陣も
(取材・文/France10・及川健二)